算数は解き方を覚えることから
ブログFROM 笠井伸春

今日はひとつ、算数の問題を。
小・中学生のお子さんをお持ちのお父さん、お母さん、挑戦してみませんか?
問題
「2を2016回かけた数の、一の位の数は?」
2016年にちなんだ中学入試でよく出題されるパターンの問題。
多分、今年もどこかの中学では出題されたのではないかと思います。
さあ、いかがでしょう?
多分、初めて見たら「え?そんなの難しい」って思うと思います。
さて、解き方は・・・
まず、実際にかけてみて見当をつけます。
1回:2
2回:2×2=4
3回:4×2=8
4回:8×2=16
5回:16×2=32
6回:32×2=64
7回:64×2=128
8回:128×2=256
・・・
一の位だけ調べると、
2、4、8、6の繰り返しになっています。
4つで1セットの繰り返しなので、
1番目が2なら、5番目も2になりますね。
つまり、
4で割ってみてあまりが1なら、1番目と同じ「2」
4で割ってみてあまりが2なら、2番目と同じ「4」
4で割ってみてあまりが3なら、3番目と同じ「8」
4で割ってみてあまりが0なら、4番目と同じ「6」
今回は、2016回かけるので、
2016÷4は割り切れる(あまりなし)
なので、答えは4番目の「6」
・・・
どうでしょう。
知らないと解けないですよね?
でも、やり方を知っていればあっという間にできます。
実際、中学入試ではよく出ています。
こういう普段の勉強では出てこないパターンの問題は
そんなに種類は多くありません。
この問題でも類題を2つ3つやって
やり方さえ暗記すれば次から解けるので大丈夫です。
よく、「考える力」が大事だと言われてて、
理数科目は「暗記すること」を軽視する人もいますが、
実際は順番が逆なんですよね。
まずは、
丸暗記するつもりで「解き方を覚えること」
それを積み上げていくとこで、応用できる範囲が広がっていくので、結果「考える力」が身についていきます。
高志中学が話題になっていますが、
もし、中学受験を考えているなら5年生くらいから準備しておきたいですね。
笠井伸春
>> 笠井伸春ブログ一覧 <<
◆執筆者紹介
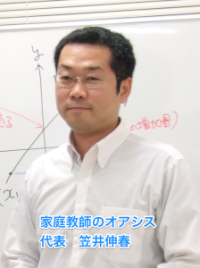
笠井伸春
家庭教師のオアシス代表
ふくい家庭教師ナビ(カテナビ)主宰
単に目先の点数を上げることだけではなく、自信につなげ、いかに生徒が自分から学習できるようになるか、自立した学習が身に付くようなサポートを目指す。
高校入試対策のため勉強方法を教えた中学生が、高校でも実践し伸びていることを知り
「1回のテストのために得た知識はテストが終わったら価値がなくなるけど、一度身につけた勉強方法はその先もずっと使える能力なんじゃないか?」
と考え、勉強のやり方を教える家庭教師のチームを作る。
主眼にしているのは、
- 能力に関係なく学習効果の高い勉強方法を身につけてもらうこと
- 成果につなげるため、家庭教師の授業がない日でも効果的な家庭学習が自分でできるようになること








