相手の使っている言葉じゃないと伝わらない(伝え方のコツ)
ブログFROM 笠井伸春
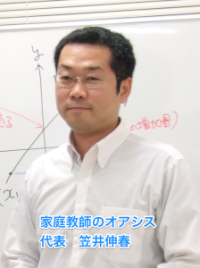
昨日のお話。
久しぶりに車を乗り換えました。マニュアルミッションの車。もともと車の運転は好きな方なので乗りたかったのですが、MT車は14年ぶり。
それで、念のために妻も運転できておいた方がいいだろうということで、マニュアル操作の練習に付き合うことに。
(妻はMT車の免許あるけど、以来あまり乗ったことがない。普通そうですね・・・)
広い駐車場の一角。
妻が恐る恐る発進しようとすると、、やはりエンジンストップ。まあ仕方ないです。そのための練習ですから。
再度エンストしそうになった時、「クラッチ切って」とアドバイスしました。
すると、、なぜか、すぐさまエンスト。
僕「え、なんで急にクラッチつなぐの?回転止まりそうになったらクラッチ切って調整しなおせばいいやん」
妻「え?え?」
繰り返すエンスト・・・。
僕「だから!慣れるまでは切ってから半クラ当て直せばいいやろ・・・」
妻「そんなんやったっけ・・・?」
このやりとりが5分ほど続き・・・あっ、と気がつきました。
妻は「クラッチを切る」を「クラッチペダルから足を離すこと」と、とらえていたのです。
なるほど、確かに運転好きじゃないと「つなぐ」とか「切る」とか分かりにくい言葉かもしれません。
「クラッチ踏む」とか「押す」って言えば最初から伝わっていたでしょう。まずかったのは、分かってると思い込んでいた僕のアドバイスでした・・・
大事なのは、相手の使っている言葉を使うこと。
これは、勉強を教えるときにも言えます。
自分の言葉は、自分が気がつかないうちに自分の環境の中で使っている言葉に変化していきます。
でも、そのままの言葉を小学生や中学生への説明に使ってもダメ。伝わりません。
自分の言葉ではなく、中学生が知ってる言葉や例えを使って解説することが大事です。
笠井伸春
>> 笠井伸春ブログ一覧 <<
PS.
もし、家庭教師を検討されているなら、家庭教師を探せるサイト「ふくい家庭教師ナビ」がおすすめです。家庭教師のオアシスの先生の一部を詳しく紹介してます。
ふくい家庭教師ナビ(カテナビ)はこちら
◆執筆者紹介
笠井伸春
家庭教師のオアシス代表
ふくい家庭教師ナビ(カテナビ)主宰
単に目先の点数を上げることだけではなく、自信につなげ、いかに生徒が自分から学習できるようになるか、自立した学習が身に付くようなサポートを目指す。
高校入試対策のため勉強方法を教えた中学生が、高校でも実践し伸びていることを知り
「1回のテストのために得た知識はテストが終わったら価値がなくなるけど、一度身につけた勉強方法はその先もずっと使える能力なんじゃないか?」
と考え、勉強のやり方を教える家庭教師のチームを作る。
主眼にしているのは、
- 能力に関係なく学習効果の高い勉強方法を身につけてもらうこと
- 成果につなげるため、家庭教師の授業がない日でも効果的な家庭学習が自分でできるようになること








